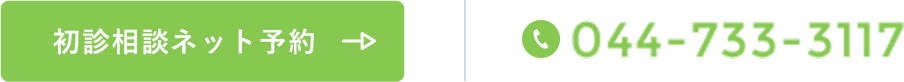パート1では、
反対咬合の具体的な症状と原因について機能性反対咬合と骨格性反対咬合の原因についてご説明しました。
今回は、2種類の反対咬合の治療方法についてご説明しましょう。
①反対咬合の治療開始時期について
反対咬合の矯正治療を開始する時期は、その症状や原因、その種類(機能性か、骨格性か)初診年齢などによっても違います。
反対咬合は、どちらのタイプであっても低年齢で早期治療を開始するのが基本的な考え方です。
家系に反対咬合を認める場合は、増齢により身長が伸びる頃には、下あごも一緒に症状がひどくなる傾向があります。
そのため、要注意な不正咬合であり治療期間は長期に及ぶことがあります。
反対咬合治療の考え方は、まず早期治療(一期治療)をおこない、
その後の歯並びや下あごの成長を観察し、必要ならば本格的治療(二期治療)で仕上げをおこなうことが基本です。
なぜならば、早期治療をおこなっても、永久歯が全て生え揃う12歳頃は下あごの成長が一番盛んな時期だからです。
歯の生える位置の異常や習慣などによる機能的な反対咬合は、
原因が局所的であり下あごの成長により影響を受けないため一期治療のみで終了することが多いでしょう。
一方、家系に反対咬合を認める場合には、身長の伸びにつれて下あごの成長が突き出してくるため要注意なのです。
そのため、矯正治療を装着で下あごの成長を抑え、上あごの前方への発育を刺激するなどをおこない長期に経過を観察しなければなりません。
家族の方にお聞きし家系に反対咬合の人が見当たらない場合であっても、
成長期に身長の伸びにより下あごが盛んに発育してくるケースに遭遇することがあります。
日本人では、反対咬合が世界で一番多い国民であり、発言頻度は5~6%と言われています。
私たちが知らない先祖に、反対咬合の方がいたのかもしれません。
次のような反対咬合の症状は、早目にご相談ください
1)上下の前歯が、逆のかみ合わせ
2)下くちびるや下あごが前方に出ている顔かたち
3)食べ方や噛み方がおかしい
4)サ行などの発音がはっきりしない
5)家系に反対咬合の人が多く見られる
このような症状に気づいた時には、まず私たちの矯正専門開業医にご相談ください。
治療時期が早い場合には、矯正歯科医院で定期的に経過観察を行います。
治療開始時期の目安を、フローチャートにすると・・
まず相談
↓
早期治療が必要な場合には一期治療
↓
一期治療終了後、歯並びや下あごの成長観察
↓ ↓
治療経過が良い場合には終了 仕上げが必要な場合には二期治療開始
但し、患者さんが最初に矯正歯科医院を訪れる年齢により、二期治療から開始することもあります。

②反対咬合のタイプと、用いる矯正装置について
機能性反対咬合の場合
機能性反対咬合は、一期治療(早期治療)だけで済む可能性があり、矯正治療後の経過は良好なものが多いと言えます。
習癖などで唇や舌などの口の周りの筋肉機能のバランスが崩れている場合は、筋肉のトレーニングを行います。
舌が下の歯列の中で低い位置にある場合(低位舌という)には、下の前歯を前方に押すため舌を持ち上げる訓練や装置を用いることがあります。
一般的に、上下の前歯の生え方の異常により、干渉して反対咬合になっている場合には、歯の位置を矯正装置の力で移動して歯の干渉を除く治療をします。
使用する装置は、口の中で取り外しができる方式や口のなかに固定する方式の矯正装置を用います。
骨格性反対咬合の場合
骨格性反対咬合の人の顔の骨格は、上あごが小さく(前方への発育がわるい)下あごが大きく(前方への発育が過剰)て、顔つきは下あごが突き出ています。
一般的に、骨格性反対咬合は、低年齢で上あごの成長を促し、下あごの成長を抑えて上下のあごの前後差を改善する矯正装置を用います。
この装置は、「上あご前方牽引装置」と呼ばれ、主に夜間装着してあごの成長をコントロールします。
骨格性反対咬合は、一期治療後のあごの成長や歯並びを観察して二期治療が必要になることが多いタイプです。
二期治療の仕上げは、歯の表面に部品をつけた固定式の装置(マルチブラケットと呼ぶ)でワイヤーの弱い力で歯を移動して治療をおこないます。
また、上の歯列が狭い症状(狭?歯列と呼ぶ)では、歯列や上あごを横方向に拡大して発育を刺激するような装置を用います。
反対咬合の家族性が強い場合、矯正装置により成長発育をコントロールができない場合や成人で骨格の改善を必要とする場合(顎変形症と呼ぶ)では、
大学生になり成長が終了した時期に矯正治療と外科手術を併用する治療法が必要になることもあります。

③反対咬合の矯正治療は、早目に矯正歯科医にご相談下さい
反対咬合は、他の不正咬合と違い咬み方、のみ込み方、発音などお口腔機能への障害があります。
また、思春期に下あごの過剰な成長発育による精神面への影響があると考えられています。
そのため、お子さんの将来を考えて反対咬合は、低年齢時に矯正治療を開始することが望ましいのです。
学校の歯科健診で不正咬合と指摘されたり歯並びが気になった時点で、まず、私たち矯正歯科専門開業医にご相談されることをお勧めします。
医院選びは、長期的な矯正治療が必要になることが多いため、経験豊富な矯正歯科専門の歯科医師が常勤していることが大切です。
本やインターネットなどで自己判断されることは、適正な治療時期を逃す場合があります。
まず経験豊富な矯正歯科医にご相談下さい。
参考文献:日本臨床矯正歯科医会 神奈川支部